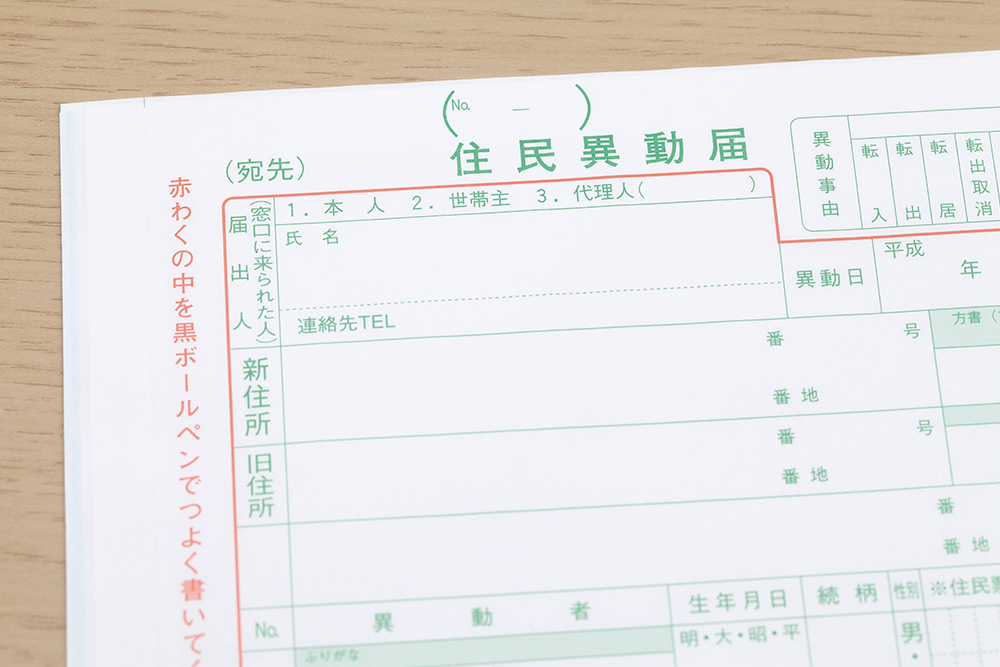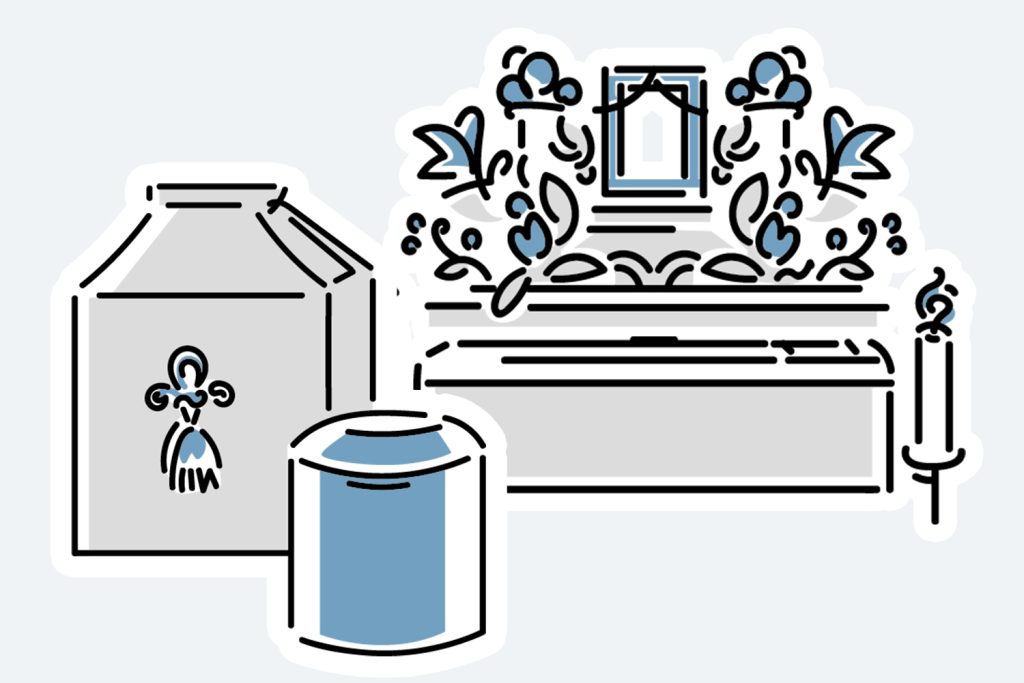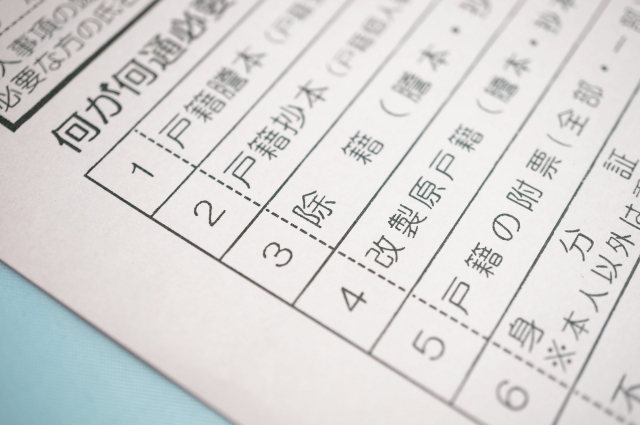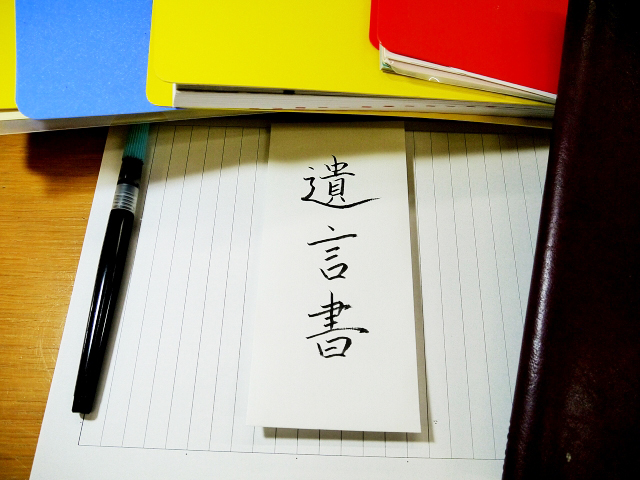-

世帯主変更届の書き方や提出先は?夫の死亡時の手続きを解説
【世帯主変更届の提出先と提出期限は】 世帯主が死亡したときに行う必要があるのが、世帯主変更届の提出です。ただし、全員が必ずしもこの手続きを行わなければいけないというわけではなく、死亡した世帯主の世帯員が15歳未満の子供である場合や、世帯主の... -

代襲相続
代襲相続とは、民法により定められた事由によって相続人の代わりに、その子どもが相続人になる制度です。 【代襲相続の発生】 代襲相続は、本来遺産を相続する相続人の代わりに、その子どもが相続する制度でありますが、この代襲相続が発生する要件は以下... -

延納制度のあらまし
相続税については相続した財産(遺産)について税金が課され、相続財産の中には即時に換金することが困難なものもあることから、納税することができない場合が存在します。相続税額を納税することが困難な場合の手続きに「延納制度」があります。 【延納申... -

葬儀から納骨や火葬許可申請書など相続時の手続き
【火葬許可申請書はどこへ提出するのか】 火葬許可申請書とは、火葬許可証を交付してもらうために必要な書類です。故人の火葬を行うためには火葬許可証が必要になるため、火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を発行してもらう必要があります。火葬許可申請... -

相続手続きに必要な戸籍謄本・戸籍抄本
【なぜ戸籍謄本が必要になるのか。さかのぼって確認が必要なのか。】 相続手続きを行うにあたっては相続人の確定が不可欠です。戸籍は転籍や法改正、婚姻により都度新しく作成されますが、その際に既に抹消された事項は基本的に新しい戸籍に記載されるもの... -

検認とは
被相続人の死後、部屋から遺言書が見つかった。そんな時は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 【検認とは】 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在に... -

小規模宅地等の特例 特定居住用住宅地等に適用する場合
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%も減額できる制度になっております。今回は小規模宅地等の特例を特定居住用宅地等に適用する場合について説明します。 【特定居住用宅地等の要件】 特定居住用宅地等とは被相続... -

代表相続人の選出と役割について
【代表相続人とは?】 遺産相続の手続きに複数の相続人がいる場合に、代表して、相続に関するさまざまな手続きを行う方が代表相続人です(相続代表者と呼ばれることもあります)。代表相続人は、税務署での相続税の支払いや、金融機関での遺産の口座の解約... -

預貯金と株式の名義変更と必要な書類について
相続発生時に注意しなければいけないのが預貯金及び株式の名義変更手続きです。どのあたりに注意すべきか、ネックになってくるかなど確認していきたいと思います。 【死亡による預金の凍結】 相続発生後、銀行をはじめとする金融機関にその旨を連絡する必... -

相続が起こった場合の生命保険金請求方法
相続が発生した後にすぐ請求できる生命保険金があったので、葬儀費用の支払いなどに充てることができてとても助かった、という人もいます。では、具体的にどのように請求したらよいのか、またその注意点などを見てみましょう。 【生命保険についてするべき...