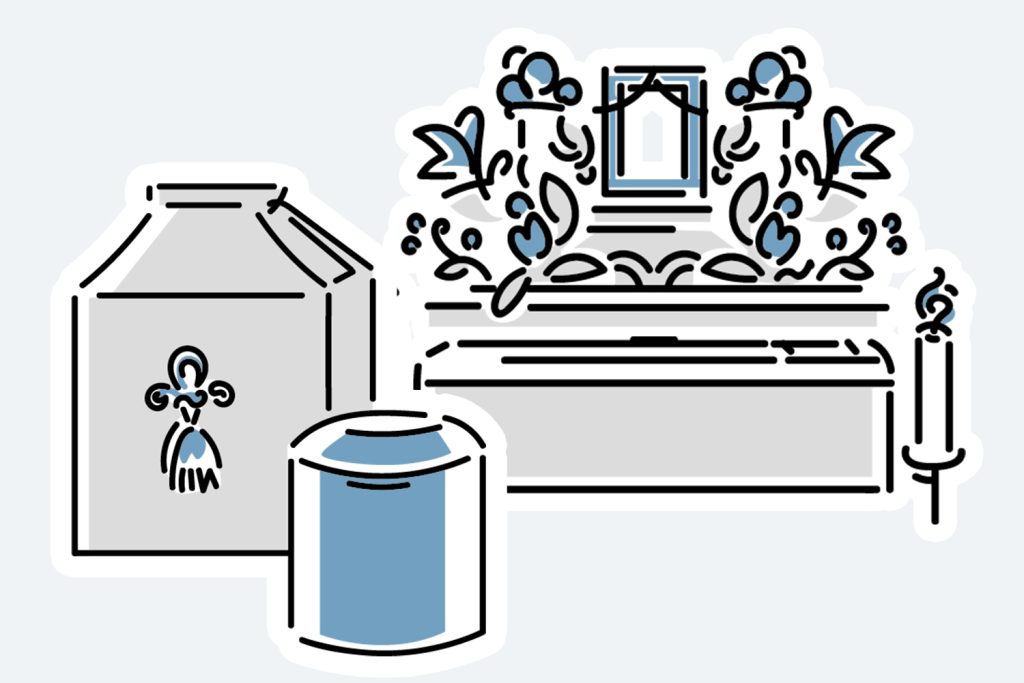記事リスト
-

【相続財産の範囲】相続税がかかる財産とかからない財産とは
相続財産の中にも相続税がかかる財産と相続税がかからない財産が存在します。相続財産の範囲、相続税がかかる範囲にはどのようなものが含まれるのでしょうか。以下で説明していきます。 【相続財産の範囲とは】 相続財産とは、民法第896条では「被相続人の... -

相続放棄 手続きの流れ・スケジュール・注意点について
相続放棄の手続きは期限が短い上に、手続き自体が複雑です。事前に手順を理解し、円滑に相続放棄を行うために、手続きの流れ・スケジュール・注意点について解説します。 【相続放棄の流れ・スケジュール】 相続放棄の期限は、相続の開始があったことが判... -

相続放棄すべき人とは?4パターンの解説と注意点
相続放棄とは、相続人が自己のために開始した相続の効果を否定し始めから相続人ではなかったことにする意思表示です。前提として相続は「プラスの財産」のみではなく「マイナスの財産」も遺産として相続人が引き継がなければいけません。相続放棄は、被相... -

代襲相続
代襲相続とは、民法により定められた事由によって相続人の代わりに、その子どもが相続人になる制度です。 【代襲相続の発生】 代襲相続は、本来遺産を相続する相続人の代わりに、その子どもが相続する制度でありますが、この代襲相続が発生する要件は以下... -

相続税の基礎控除
相続をした際、必ずしも相続税額が生じるわけではありません。被相続人から相続人が相続した財産(遺産)の価額が基礎控除額を超える場合に、相続税額が生じます。この基礎控除額については、一律で適用される部分が3,000万円あるのと、法定相続人の数によ... -

相続時における銀行預金の解約や名義変更について解説
【相続財産としての銀行預金に係る相続手続き】 亡くなられた方(被相続人)の 銀行預金口座は、死亡した日に相続人の相続財産となります。そして、相続人が複数人いる場合は、すべての相続人の共有財産となります。 そのため、被相続人の 銀行預金口座の... -

延納制度のあらまし
相続税については相続した財産(遺産)について税金が課され、相続財産の中には即時に換金することが困難なものもあることから、納税することができない場合が存在します。相続税額を納税することが困難な場合の手続きに「延納制度」があります。 【延納申... -

葬儀から納骨や火葬許可申請書など相続時の手続き
【火葬許可申請書はどこへ提出するのか】 火葬許可申請書とは、火葬許可証を交付してもらうために必要な書類です。故人の火葬を行うためには火葬許可証が必要になるため、火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を発行してもらう必要があります。火葬許可申請... -

復氏届と姻族関係終了届の提出方法
配偶者が亡くなってしまった場合、これまで名乗っていた姓を婚姻前の旧姓に戻す際に提出しなければならない届出があります。また離婚などにより姻族関係を終了させる際にも届出を提出する必要があります。前者の場合を「復氏届」といい、後者を「姻族関係... -

相続が発生したら免許証やクレジットカードはどうする?
【死亡後の免許証の返納手続】 道路交通法では、明文で規定されていないものの、免許証の保有者が死亡した場合には免許は無効になるものと解釈されています。そのため、保有者が死亡した場合、遺族が保有者に代わってすみやかに免許証を警察署もしくは運転...