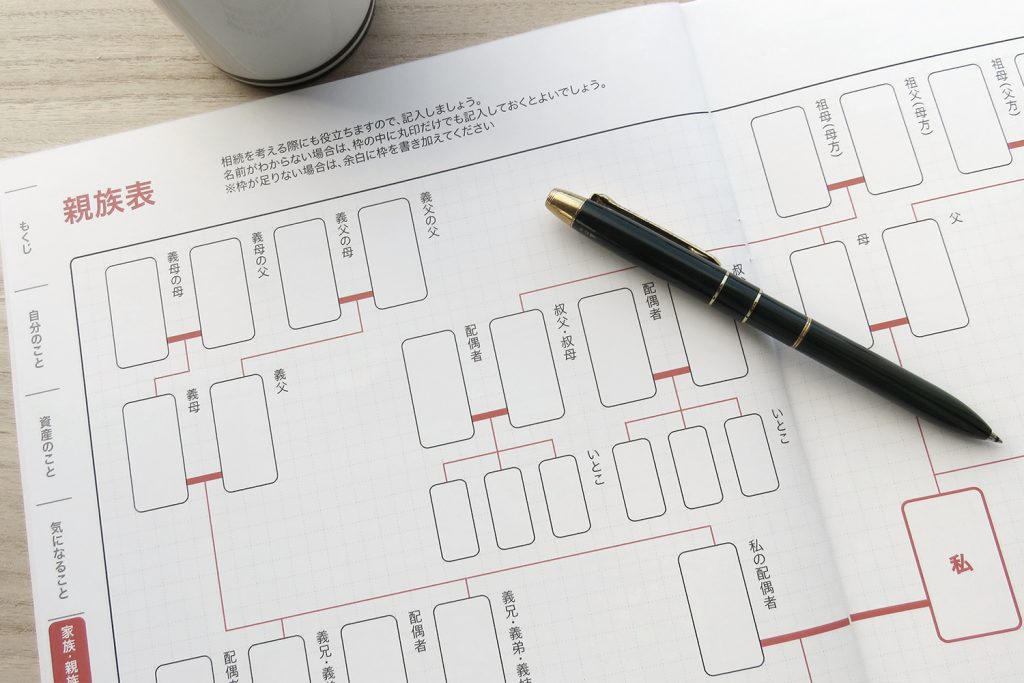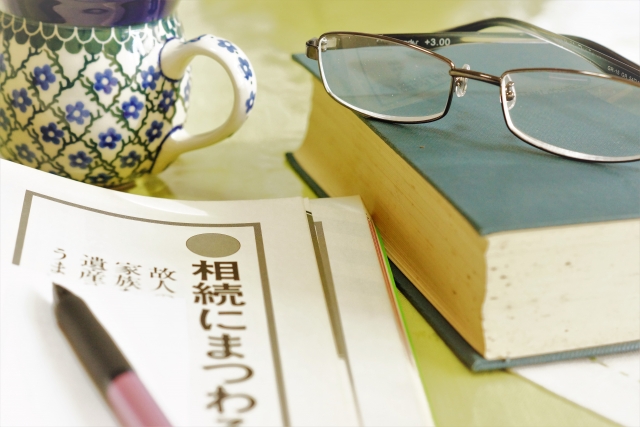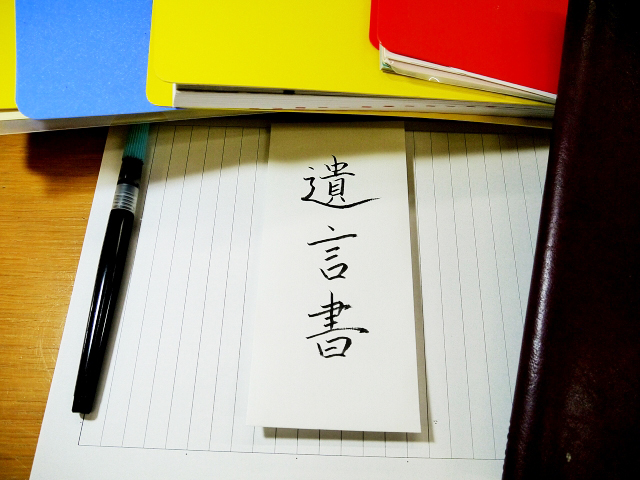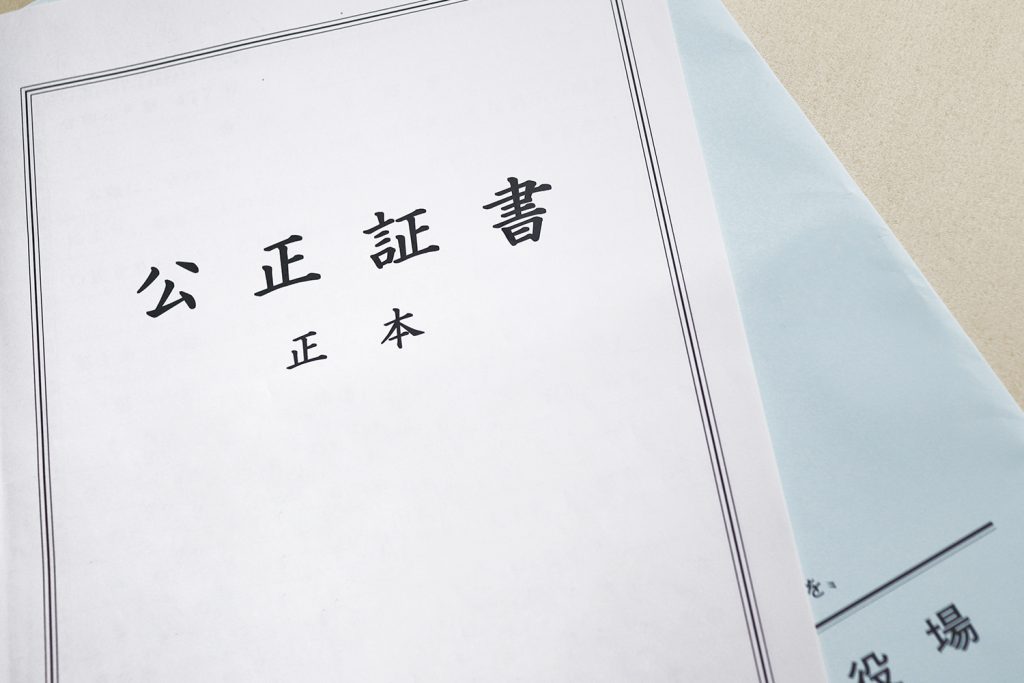記事リスト
-

未婚のいとこが亡くなった場合の相続について
民法において相続人となり得る者には順位が定められています。遺言がある場合には、遺留分を除いて遺言が優先されますが、遺言がない場合には法定相続順位に従って相続が行われます。 未婚のいとこが亡くなった場合、そのいとこに子がいるときは、子及びそ... -

債務控除とは
相続税は、相続または遺贈により受けた利益にその担税力を求めて課税される税金ですから、その財産の取得者が被相続人の債務を承継して負担するときや、被相続人の葬式に要した費用を負担するときは、その負担分だけ財産の価格から控除して相続税の計算を... -

相続にまつわる期限
相続については、申告・納付期限のほか、納税することが困難なため相続を放棄する相続放棄や、被相続人の亡くなった年に行う所得税申告である準確定申告など、期限が定められているものが多々あります。本テーマでは、メインである申告・納付期限とそれ以... -

検認とは
被相続人の死後、部屋から遺言書が見つかった。そんな時は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 【検認とは】 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在に... -

公正証書遺言の作成手順
【公正証書遺言とは?】 公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間... -

生命保険金にかかる相続税評価方法は?
生命保険金に対してかかる税金はその保険料を誰が支払っていたかによって異なります。生命保険をうまく活用することで節税ができるため、いろいろなパターンについて考えていきます。 【保険の契約により課される税金が異なる】 保険料負担者と保険金受取... -

家なき子特例
【概要】 小規模宅地等の特例はその宅地等を相続または遺贈により取得する相続人が、被相続人の配偶者、被相続人の居住の用に供されていた一連の建物に居住していた親族が受けられる特例です。しかし、家なき子特例は、相続人が被相続人と別居していたとし... -

相続財産を見つける手がかりとは?
被相続人が死亡をすると相続が発生します。ここでは被相続人の財産はどのようなものが含まれるのか、その財産はどこにある可能性が高いのか説明していきます。 【相続財産に該当する範囲】 相続財産の範囲は原則として「被相続人の財産に属した一切の権利... -

空き家の相続税は人が住んでいる家より割高?相続税の計算方法と節税対策
相続税には小規模宅地等の特例という制度があります。被相続人が生前に居住していた土地を相続人が相続する場合に、一定の要件を満たすことで評価額を80%減額することができるというものです。しかし、空き家については居住していないことからこの特例は適... -

遺贈とは
遺贈とは、遺言によって他人に財産を与えることです。生前における財産処分の自由を死後にまで及ぼすもので、相続人以外の人にも遺産を与えることができます。 【遺贈の種類】 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の二つがあります。いずれの遺贈も負担付にした...