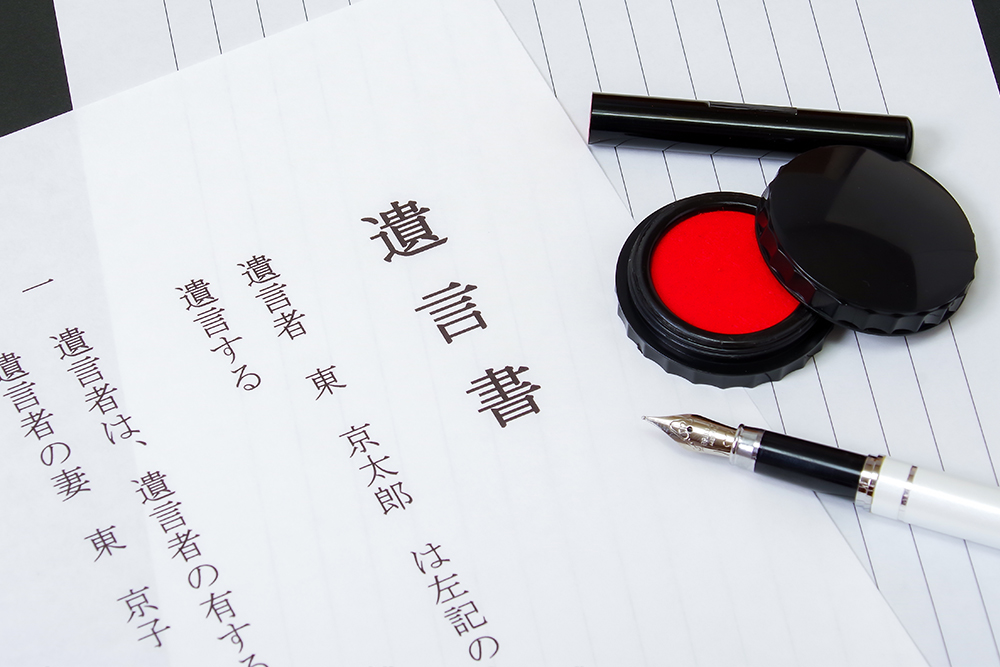遺言書を作成するメリットとは?
遺言書が存在しない場合、遺産の分割は相続人間の協議によって決定されます。各相続人が合意すればどのような分割も可能ですが、合意が成立しない場合は、調停や審判を通じて解決を図る必要があります。争いが続くと最終的には法定相続割合が適用され、後継者が必要とする株式や事業用の資産を集中させることが難しくなります。
目次
遺言書作成時の留意ポイント
- 遺留分について意識をもつ
「後継者以外の相続人に自社株を相続」させるのは、将来的に「後継者が事業を継続」するうえで、大きな障壁となる可能性があるため、避けるべきです。ただし、留意すべきポイントは、後継者のことだけを考えるのではなく、後継者以外の相続人についても気を配りながら、特に遺留分を侵害しないようにバランスを取ることが重要です。 - 遺留分とは
遺留分とは相続人となる人に法律で権利として保障された最低限の相続財産のことです。遺留分割合は法定相続分の1/2(直系尊属のみは1/3)となります。
| 相続人の内訳 | 遺留分割合 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 直系尊属のみの場合 | 被相続人の財産の3分の1 | 民1042I① |
| 上記以外の場合 | 被相続人の財産の2分の1 | 民1042I② |
遺留分の対策方法は?
後継者以外の相続人への遺留分対策としては主に6つです。
- 付言事項でメッセージを残す
遺言書の末尾に「付言事項」の項目を設けて、なぜこのような遺言にしたかということを明記しておくことが重要です。 - 生前からの十分な説明
生前から相続人に対して、なぜこのような遺言にしたかということを、誤解のないように十分に説明した上で、理解を得ておくことが無用な紛争を防止するために大切です。 - 後継者が資金を準備しておく
後継者が遺留分について代償金で支払うなど資金の準備をしておきます。 事前に遺留分の支払いに必要な金額をシミレーションして遺産を遺したい人の手元に資金を確保しておきましょう。代償金の準備としては、死亡保険金や死亡退職金を活用し後継者が受取れるようにします。 - エンディングノート等の活用
残したいメッセージについて、今流行のエンディングノートに書くとか、ビデオレターで残すなどすれば、意志や考えをより遺族の方に伝えやすくなるでしょう。 ただし、これは法的な拘束力はないためご注意ください。 - 遺留分の放棄を検討
遺留分を請求しそうな相続人がいる場合、生前に遺留分を放棄させます。 これは、遺留分を放棄すべき合理的な理由があるなど一定の要件をクリアした場合で家庭裁判所の許可申立てが認められなくてはできませんので、ハードルは高いといえます。
| 後継者に株を集中させるための「除外合意」と「固定合意」 | |
|---|---|
| ↓ | |
| 除外合意 | 固定合意 |
| 生前贈与された株式等を遺留分から 除外するという合意 | 自社株の遺留分の評価額を合意時点 で固定するという合意 |
固定合意は最終的な遺留分の問題が残るため、除外合意の方がリスク少なくお勧めできる合意です。
事業承継で最適な遺言書とは?
- 人はいつ、亡くなるかわからない
安定した事業の継続を望む経営者としてありがちなのが、つい頑張り続けて事業承継の好機を逃してしまうことがあります。どのタイミングで後継者へ事業を引き継ぐか考えている間に、突然亡くなられてしまうこともあります。 万が一に備えるうえで、早い段階から遺言書を残すことも必要です。 - 事業承継で最適な遺言書の種類は
法律上、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はともに遺言書として認められているので、どちらであっても問題はありません。ただし、事業承継を万全にするために、やはり公正証書遺言のほうが望ましいといえます。 自筆証書遺言は法律上厳格な形式要件が定められており、もし満たしていない場合は法的効力が認められない可能性が高いからです。 - 公正証書遺言について
公正証書遺言は、2人以上の証人が立会って、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記し、証人に内容を確認したあと、各自署名押印し、公証人が署名押印する方式のことをいいます。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されることになります。公正証書遺言は家庭裁判所での検認の必要はありません。 - 自筆証書遺言よりもメリットが多い公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が作成するので、無効になることはほとんどなく、あまり心配する必要はないでしょう。
【公正証書遺言のメリット】
- 法的に間違いのない遺言を作成できる
- 字を書くことができなくても口頭で可能
- 家庭裁判所で検認の手続きをしなくていい
- 偽造や紛失の恐れがない
遺留分対策と納税資金対策の方法
- 会社に買取り資金がある場合
後継者に自社株式を承継させたあと、会社がその自社株式を買取り、その資金で代償金として金銭を渡すという遺言書を書くとよいでしょう。 - 退職金を活用する場合
退職金を活用して相続税と遺留分を確保する際には、退職金の受取人をどのように選定するかが問題となります。遺留分対策を考えるなら、通常、後継者に全額を受け継がせるのが良いでしょう。退職金はみなし相続財産となりますが、原則として遺留分の対象からは外れるため、後継者を受取人と指定することが可能です。ただし、相続税法の観点からは、退職金には非課税枠が存在するため、配偶者以外の相続人が適切な受取人として指定されれば、相続人全体の相続税負担の観点から公平と言えるでしょう。 具体的な選択は、子供たちの人間関係を考慮して判断する必要があります。 - 生命保険金を活用する場合
経営者が生命保険金などで資金を用意しようと考えている場合、生命保険の受取人を後継者に指定するのが適切です。一般的な誤解として、遺留分に相当する財産を次男に譲渡することで問題が解決できると考える方もいますが、これは誤りです。 生命保険金は原則として受取人の財産であり、被相続人の財産ではありません。生命保険金を遺留分対策に活用する場合は、受取人を「事業を引き継ぐ長男」として指定し、代償金を用意するべきです。生命保険を代償分割に活用することで、不動産の売却や自社株の分散を防ぐことが可能です。
最後に
遺言書がないと大きなトラブルに発展する可能性は少なくありません。事業の承継や相続・遺留分、株式分散に対する対策について、早めに元気なうちから考え始め、専門家のアドバイスを受けながら計画的な遺言を作成していきましょう。